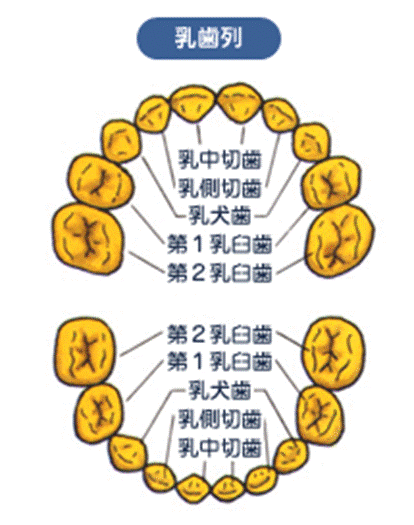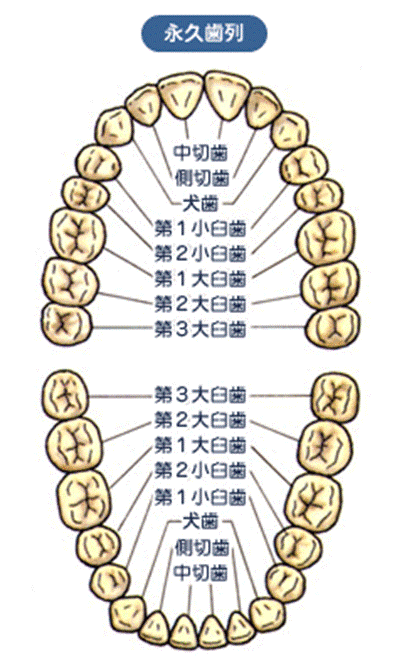1.歯のしくみと用語の説明

- エナメル質 人体の中で一番硬い組織で、歯の中で一番むし歯の抵抗力が強い部分です。
- 象牙質 歯髄(神経)のまわりを構成している部分で、むし歯でエナメル質のバリアが破られると象牙 質では速度を速め、急速に広がります。
- 歯髄 一般的に神経と呼ばれている部分です。痛みを感じる神経と、水分や栄養を供給する血管からなっています。
- 歯根膜 根の表面と歯槽骨をつないでいる組織で、かんだ時の感覚を感じる部分です。
- 歯槽骨 歯を支える部分の骨のことで、歯周病が進行すると破壊されていきます。
- 歯周ポケット 歯と歯肉の間にある溝のこと。歯周病が進むに従って深くなるため、歯周病進行度の目安になります。深さ4mm以上の歯は要注意!

・プラーク
むし歯菌や歯周病菌を含む多数の菌の魂(集合体)。つまり、むし歯も歯周病もプラークの感染症なのです。
表面が細胞外マトリックスというフイルムで覆われているため、免疫や抗生物質が効きにくい。
やわらかいが、うがいをしてもとれない。除去には、ブラッシングやPMTC(後述)が有効です。
2.歯の名前
中切歯~第2小臼歯は乳歯が抜けると生えてくる歯です。
第1~3大臼歯は乳歯と生え変わるのではなく、後ろに追加され生えてくる歯です。
3.むし歯とは
むし歯菌の作りだす酸によって、エナメル質や象牙質の成分であるカルシウムやリン酸が溶けだして、穴が開いていく状態をいいます。むし歯菌が痛みを感じる組織である歯髄(神経)に到達し、炎症を起こすと強い痛みを起こします。
お口の中では、歯が溶け出す状態(脱灰)と、溶けた歯を修理する状態(再石灰化)が日常的に繰り返し起きています。
このバランスが崩れ、脱灰が再石灰化を上回る状態が続くとむし歯になります。それではなぜ、歯は脱灰するのでしょうか?
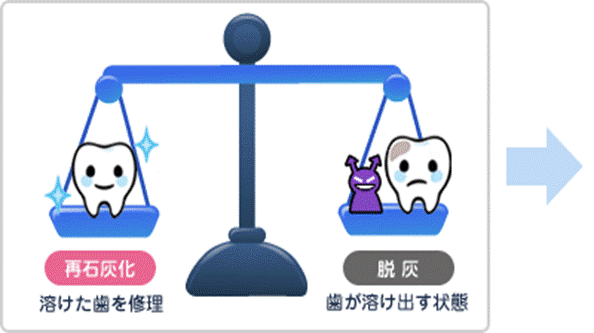

【脱灰の条件】
虫歯菌・・・むし歯菌はプラークという菌の魂をつくり、お口の中で糖分を栄養として酸をつくります。
糖 分・・・糖分はむし歯菌のエネルギー源になります。
むし歯を作らない為には・・・
- ブラッシングにより菌の魂であるプラークを除去し、むし歯菌を減少させ酸を作りにくい状態にする。
また、プラークの付着していない歯の表面は、唾液による再炭化が促進されます。 - 食事終了後すぐにブラッシングをする。
(食事開始後すぐにお口の中は酸性になり脱灰が始まります) - 糖分の適正な摂取を心がける。
絶えず間食し食べ物が口の中に入っている時間が長いほど、脱灰量は多くなります。 - フッ素を使用して、酸により脱灰しにくい歯の表面を作る。
4.むし歯のできやすい場所
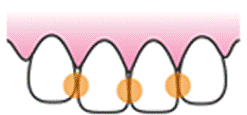
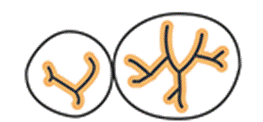


【1~3】はブラシが入りにくく、プラークが蓄積しやすい場所。
【4】はエナメル質が無いために、酸に対する抵抗力が弱い場所です。
この他にも、歯と歯が重なっている場所や合っていないつめ物やかぶせ物が入ってる所など、人によりむし歯の出来やすい場所は変わりますが、大事なことは歯科医院でプラークの付着を確認し、歯科衛生士に適切なブラッシングを指導してもらい、プラークをきちんと除去することです。
自己流のブラッシングでは、むし歯菌に通用しない場合が多いのです。
5.むし歯の予防にはフッ素が有効!
WHOは2021年に「人々が健康を保つために必須の医薬品のリスト」に歯科領域から3製剤を選びました。その中の1つがフッ素です。フッ素には、以下のような効果があります。
- エナメル質の修復を促進
酸により歯から溶け出したカルシウムやリンを補うことで再石灰化を促進します。 - 歯の質を強化
エナメル質の表面を、酸に溶けにくい性質に変え、ムシ歯への抵抗力を高めます。 - 菌の働きを弱める
むし歯を引き起こす細菌の働きを弱め、酸がつくられるのを抑えます。
当院では、院内で行う超高濃度(9,000ppm)フッ素の塗布(フッ素コート)を行っております。
また、むし歯リスクの高い方向けには、ご家庭で行うフッ素洗口(うがい)を推奨しております。歯科医師が年齢やむし歯のリスクに応じて250~900ppmの濃度範囲で回数、頻度調整の上、使用説明・処方しております。ブラッシングの後にフッ素洗口をすることで、フッ素が歯の表面に長くとどまり、効果が持続します。
※市販の歯磨き粉にもフッ素が最大1,450ppm含まれておりますが、歯磨きの最後に水でうがいをすることで、薄められ流してしまうので、フッ素としての歯磨き粉の効き目は限定的になります。
虫歯予防には、フッ素を使用した洗口(うがい)のほうが、効果的です。

(ミラノール顆粒)
6.むし歯の進行
(進行度によってCO,C1,C2,C3,C4と分類します)
エナメル質のごく表面が脱炭した状態(CO)は、適切なブラッシング等によって再石炭化が可能ですが、C2以降の象牙質内部まで進行したむし歯は、早めの治療が必要です。

C1ーエナメル質のみが酸によって溶けた状態
歯の色がチョークのような白色、又は茶褐色に変わる。全く痛みはない。
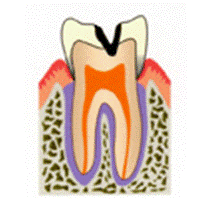
C2ーエナメル質に完全に穴が開き、象牙質までむし歯が広がった状態
むし歯が歯髄に近づくと、しみる場合もある。歯髄に細菌が侵入していないので、むし歯を除去しつめ物をすることで治る。

C3ーむし歯が歯髄まで進入、つまり歯髄が細菌感染をおこした状態
穴も大きくなり、食べ物が詰まると痛んだり、夜中に眠れない程痛むことも。歯髄を温存できる場合と、歯髄を除去しなければならない場合がある。

C4ー歯ぐきから上はむし歯で崩壊し、歯髄も死んでしまっている状態
根の先端に膿の袋ができ、腫れてくることもある。根の治療をして歯を保存するか、抜歯が必要な場合もある。
7.むし歯の治療
C0~C1(初期の虫歯)
むし歯が歯の表面にあるエナメル質がわずかに脱灰している場合から、エナメル質内に留まっている場合は、基本的に歯を削りません。その理由は、きちんとブラッシングを行うことでむし歯の進行を止め、再石灰化を期待することが出来るからです。
ただし、表層がむし歯になったという状態がこのまま続けば、今後むし歯は確実に進行します。歯科衛生士のブラッシング指導をよく聞き、プラークをしっかり落とすように心がけましょう。フッ素の塗布も効果的です。
C2(象牙質に進んだ虫歯)
むし歯が象牙質まで進行すると、進行速度も速まり、再石灰化も期待できません。基本的にむし歯の部分を除去し、詰め物をしたり、被せ物をする治療になります。歯髄(神経)が残っている歯では、治療時麻酔をするのが一般的です。
詰め物の種類には、コンポジットレジン充填とインレー修復があります。
コンポジットレジン(CR)充填
合成樹脂の詰め物です。むし歯の部分を取ったあとに、ペースト状のコンポジットレジンをつめ、特殊な光を当てて固めます。歯と同じ様な色をしているので、審美的な詰め物ができますが、長時間では多少の変色がみられます。
前歯のむし歯や、奥歯の溝の部分のむし歯の治療に使用します。健康保険適用で1回で治療が終了します。
インレー修復

むし歯を除去し、歯型を取り、模型上で詰め物をしてから製作し、お口の中で細かい調整をしてから接着剤でつけます。奥歯の歯間の部分を含むものや、ある程度広範囲に広がったむし歯の治療に使用します。
乳歯に使用する銀合金や永久歯に使用する金銀パラジウム合金(どちらも銀色)、CAD/CAMインレー(歯牙色)は健康保険適用ですが、金合金やセラミックを使用したものは保険外治療(自費治療)となります。
- ※C2状態でもむし歯の範囲が広い場合は、被せ物をする場合もあります。
- ※アマルガムについて・・・アマルガムとは、水銀・銀・すずの合金。詰めるときは軟らかく、間もなく硬くなる素材で、 奥歯の溝や前歯の裏側のむし歯の治療に使われます。保険適用ですが、水銀を含む合金は体に良くないため、当院では全く 使用しておりません。
C3(歯髄に及んだ虫歯や歯髄を取った歯の再治療)
むし歯が象牙質を通り抜け、歯髄に達すると、歯髄には細菌が入り込んだ状態となります。無症状の場合もありますが、水がしみたり、むし歯の穴に物が詰まって痛んだり、あるいは眠れないほどひどく痛んだりする場合があります。
必要に応じて根管治療を行い、クラウン(かぶせ物)を入れ、歯の残った部分が欠けないように補強します。
8.健康保険適用の白い歯
健康保険の範囲で治療を行っても銀歯ばっかり・・・ではありません。最近は、保険の治療でも「白い歯」の適用範囲が広がってきています。
① コンポジットレジン充填~比較的小さいむし歯の治療に向いていますが、むし歯を取り除いた部分にコンポジットレジンという歯の色をした樹脂を詰め、青色光を当てて固めます。一回の治療で完結します。
② 硬質レジン前装冠~かぶせ物をする場合に、金属で枠組みを作ったかぶせ物の表側(外側)にコンポジットレジンを貼り付けたタイプ。一本一本歯科技工士が手作業で製作します。単独のかぶせ物は中央から3番目の犬歯まで、ブリッジの支えになる場合は第2小臼歯まで適用。


③ CAD/CAMクラウン、インレー~CAD/CAMとは、Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturingの略でコンピューターを用いた設計と製造支援を言います。模型をスキャナーで読み取り、高強度レジンブロックという既製品のブロック(セラミックではありません)をコンピューター上の設計を基に削り出して製作します。
基になるブロックが既製品のため、細かい色は合わせることはできませんが、まったく金属を使用しないタイプで、銀歯と比べるとかなり自然感が得られます。中央から5番目の第2小臼歯まで適用、奥の大臼歯部は条件付き適用になります。ただし、ブリッジには適用不可で、単独冠のみの適用です。