1.治療を始めるにあたって

お子さんの歯科治療を行うにあたって、大人の治療と異なるのは「心も体も発達段階にある」ということです。
これから一生付き合っていく歯というものを、乳歯から永久歯へいかに良い状態でバトンタッチさせ、それを生涯保っていくか。このスタートを切るのが、子供の時期の大切さになります。
そこで当院が大切にしているのが、「歯医者をこわがらないように、きらいにならないように」ということです。これがクリアできれば、大人になってからも歯医者に行くのがいやだからという理由で、むし歯や歯周病を放置するということがなくなってくると思うからです。
ですから、歯科治療が生まれて初めてというお子さんの治療は、(はじめから治療は大丈夫というお子さんを除いて)スタッフと友だちになったり、口の中を見せてもらったり、治療器具に触ったり動かしてみたりと、不安や警戒心を取り除くことから始めていきます。
その後の経過をみながら、口の中で器具を動かすことに慣れてから治療に入っていきます。 最初は「3つ数える間だけ口を開いていようね」から始め、徐々にがんばれるようにしていきます。この時点で「歯医者さん面白かった」とか、「違う器械もやってみて!」というお子さんもけっこう多いのです。そのために大事なのが、大人が先入観を与えないということです。
下記に、お子さんの歯科治療をスムーズに進めるための秘訣を挙げてみますので、どうぞ参考にしてみてください。
2.歯科治療をスムーズに進めるための秘訣
歯科治療に対する先入観を与えない
「言うことを聞かないと歯医者に行って注射してもらうよ」「歯を抜いてもらうよ」など、普段から歯医者=怖いところというイメージを連想させることを軽い気持ちで言わないようにしましょう。
治療する段階になって「怖くないからね、痛くないからね」と言っても遅いのです。
治療内容をお子さんと約束しないように
「今日は何もしないからね」「見るだけだからね」と、保護者の方がお子さんを歯科医院に連れて行くためにこういった約束をしてしまうと、結果として約束を守れなくなる場合もあり、不信感を生む結果になってしまう場合があります。
私たちはお子さんとの約束を守りながら信頼関係を築いていきますので、この点はよろしくお願いいたします。
治療が終わったら、たくさん褒めてあげてください
泣いて治療があまりできなかったとしても、子供たちは常にがんばっています。治療が終わったら必ず褒めてあげてください。前回できなかったことが1つでもできたら、大げさに褒めること、それが次の進歩を生みます。
今回泣いてできなかった治療が、次は突然できるようになることもあるのです。
3.子どものむし歯の特徴

子どもの歯の特徴として「むし歯の進行が速い」ということが挙げられます。保護者の方が「むし歯かな?」と思うころにはけっこう大きなむし歯になっていることがよくあります。
また、(幼稚園、保育園、学校などの)集団検診では、初期~中期のむし歯が見つからないこともありますので、保護者の方に普段からお口の中を注意して見ていただくことが、非常に大切です。
下記にむし歯の見つけ方を掲載いたしますので、むし歯かな?と思ったら早めの受診をお願いします。痛みが出てからでは「慣れる」前に「すぐに治療」を始めなくてはなりませんので、お子さんに不要のストレスをかけてしまう事になります。
できればむし歯のないときから、歯科医院での健診・受診に慣れておくことが望ましいのです。
※むし歯のでき方、進み方については歯のしくみとむし歯・健康保険の白い歯「むし歯とは」をご覧下さい。
4.むし歯をみつけよう
むし歯は表面のエナメル質を通過すると、その中にある象牙質で進行速度を速め、急激に広がります。ですから下の写真のような状態でも、むし歯を全部取り除くと、この何倍もの穴になります。
むし歯が歯髄(神経)まで広がる前に発見しましょう。「むし歯かも?」と思ったら早めの受診をお願いします。特に、乳歯の奥歯の歯と歯の間のむし歯は要注意です。将来生えてくる永久歯のスペースをロスして、歯並びを悪くする原因にもなります
むし歯の例

むし歯ができています。

むし歯はもっと広がっています。


中で広がりはじめています。


5.むし歯の予防
むし歯は、図Aのように、歯・糖分・プラーク(歯垢:菌の塊)の3つが揃ったときにできます。
図Bのように、この3つの条件を1つ1つ改善していくことが、お子さんをむし歯から守る秘訣です。特にお子さんのむし歯に限っていえば、糖分の摂取の方法が原因として最も重要です。
このため下図では、図Aの糖分、図Bの食生活の改善の円を他より少し大きく書いています。
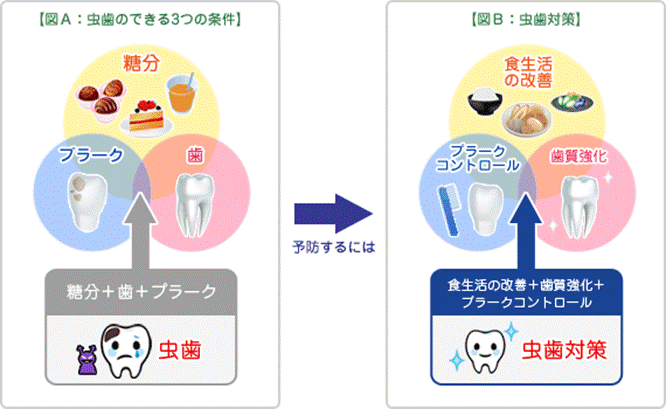
1,糖分の摂取について
子どもは3回の食事だけでは十分な栄養が摂りきれず、どうしても間食を摂るということが必要になります。しかし、お口の中は食事開始時から酸性に傾き始め、pH5.5以下になると、歯の表面は「脱灰」という歯のカルシウム分が溶け出す状態になります。(詳しくは歯のしくみとむし歯「むし歯とは」をご覧下さい) この酸性状態が長ければ長いほど、むし歯の発生・進行するリスクは高くなっていきます。
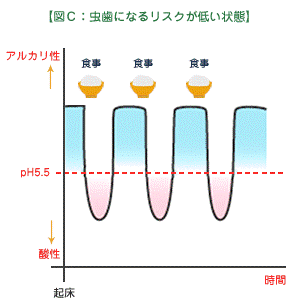
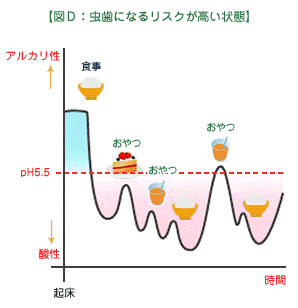
上の2つの図は、食事のパターンによるむし歯のリスクを比較したものです。
■ゾーンでは、お口の中のpHが5.5以下になり、脱灰、つまりむし歯になりやすい状態です。
■ゾーンはむし歯の危険性が低い状態です。
図Cと比べ図Dは、間食の回数が多いため■面積が大きく、むし歯になるリスクが高いことがわかると思います。
また、回数だけではなく、糖分の入った飴やペットボトルなどの蓋のついた飲み物を、長時間にわたって口に入れている状態は、むし歯のリスクを高くします。
ですから、おやつの時間を決めて与えたり、単独で飲んでいたジュースを他のおやつにまとめるなど、回数や時間を考えていくことが大事です。
2,プラーク(歯垢)対策
生まれてきた赤ちゃんのお口の中には、むし歯菌はまったくいません。主にお父さんやお母さん、つまり保護者から感染するのです。スキンシップは大切なことですが、口移しやスプーンの共用などはやめましょう。また、保護者自身が虫歯のないようにしておくことも大切です。
そして、歯が生えてくると大切になってくるのが、プラークコントロールです。
●乳歯の前歯が生えそろうまで
前歯が生えそろうまでは、濡れたガーゼ等でプラークを拭き取るようにしながら、徐々に、歯ブラシを手に持たせたり口に入れてみたりして、歯ブラシに慣らしていきましょう。
また、授乳期にはミルクが前歯の裏側に残ってむし歯の原因になります。ミルクの後にお茶や湯冷ましを少し飲ませて、残ったミルクを洗い流すのもひとつの方法です。
●乳歯の奥歯が生えそろうまで
1歳半ぐらいから乳歯の奥歯が生え始め、乳歯が全部生え揃うころに、乳歯期としては最もむし歯になりやすい時期に入ります。
むし歯になりやすい場所は、前歯の歯と歯の間、奥歯の溝の部分と歯と歯の間です。とくに歯と歯の間のむし歯は見つけにくいところなので、定期的に歯科医院を受診してチェックしてもらいましょう。
このときにフッ素塗布やシーラントなどの予防処置をしてもらうと良いでしょう。(詳しくは最後に解説します)
そして、大切なブラッシングについてですが、必ず保護者の方のブラッシング(仕上げ磨き)が重要です。歯科医院受診時に歯科衛生士にブラッシング法について教えてもらいましょう。保健所の健診でもブラッシング法についてはお話があると思いますが、1人1人の性格も口の中の状態も違うもの。個人にあったお話が聞けると思います。また、理論よりも実践が大切なのがブラッシングです。プラークがどこに残っているかを実際に見せてもらってください。
●6歳臼歯が生えるころ
6歳臼歯は乳歯の後ろに追加されて生えてくる歯で、乳歯とは生え変わりません。噛み合わせにとって非常に重要な歯ですが、溝が深く、生えてすぐのときは表面のエナメル質が未成熟のため、早期にむし歯になりやすく、歯の平均寿命も短い歯になっています。
噛み合わせの部分が歯肉の上に生えてきたら、シーラントをすると良いでしょう。このころから順次乳歯から永久歯へと生え変わっていきます。半年に1回程度のフッ素塗布が理想です。
ブラッシングにおいても、小学校低学年までは保護者による仕上げ磨きが望ましいと思います。
6.虫歯の予防処置
フッ素塗布(歯質の強化)
歯の表面にフッ素を塗布することでエナメル質にフッ素が取り込まれると、むし歯の原因である酸に対して抵抗力が強くなり、歯の成分であるカルシウムやリン酸が溶け出しにくくなります。また、再石灰化も促進されるため虫歯になりにくくなります。ただし、「フッ素を塗っているから、ブラッシングをしてもむし歯にならない」ということではありませんので注意してください。
一般的には年に2~3回のフッ素塗布が望ましいと考えられています。実際の研究では、1歳6ヶ月から2年間、半年に1回ずつフッ素塗布を行った場合、フッ素塗布しなかった場合と比べてむし歯の発生が約44%低くなったというデータがあります。
フィッシャーシーラント(予防充填)

右の写真のように、奥歯の噛み合わせ部分にある溝は、表面から見える状態よりも非常に深く細いため、歯ブラシの毛先が溝の奥まで入りにくく、むし歯ができやすい部分です。 むし歯になる前に、あるいはごく初期段階のときに、溝の部分を清掃し(歯は削りません)、樹脂で埋めてしまうのがフィッシャーシーラントです。
あくまで溝の部分のみの予防処置ですが、この部分のむし歯予防率は80%以上です。ただし、シーラントは欠けてしまうこともあり、定期的なチェックが望ましいです。
7.虫歯の治療
お子さんに不安を与えないように、なるべく痛みのない治療を心がけています。
エナメル質表面のごく初期の虫歯
ごく初期の虫歯は、むし歯のできた原因を改善することで進行を止めることができます。ですから、基本的に「むし歯を削る」という処置は行いません。しかし、現在のままの状態を続けるとむし歯は徐々に進行してしまいます。図Bのように食生活の改善、プラークコントロール(ブラッシング指導)、フッ素などによる歯の耐酸性強化などを行い経過をみます。
中期~後期のむし歯
麻酔をしてむし歯を取り除き、詰め物や被せ物をします。材料はコンポジットレジンという白い樹脂や金属です。
また、小さなお子さんで治療ができない場合は虫歯の進行止め(進行が完全に止まるものではありません)を塗布し、成長して治療ができるようになってから、本格的な治療を行う場合もあります。ただし、むし歯の進行止めはむし歯を黒く染めますので、保護者の方とご相談の上、治療方針を決めさせていただきます。
